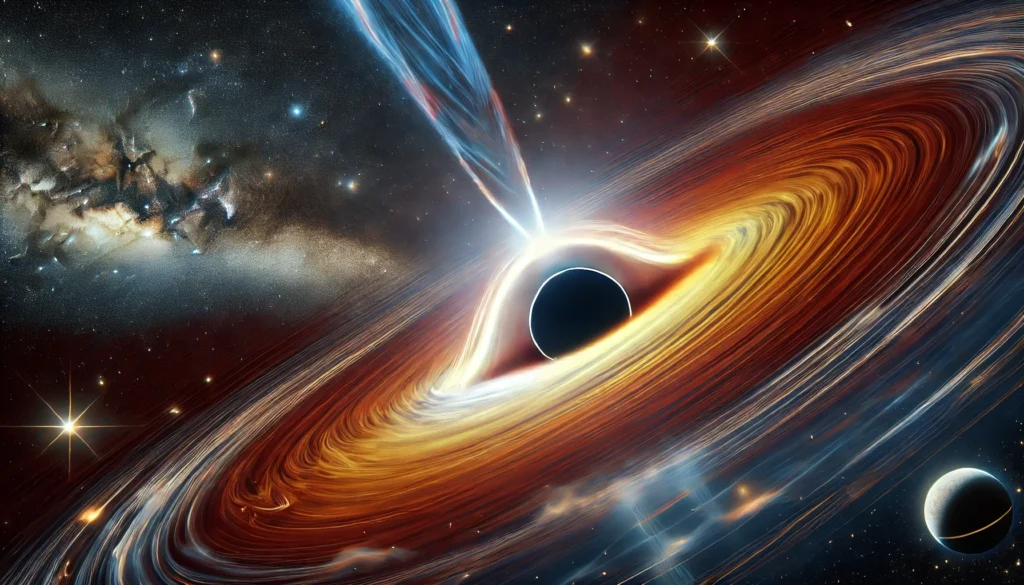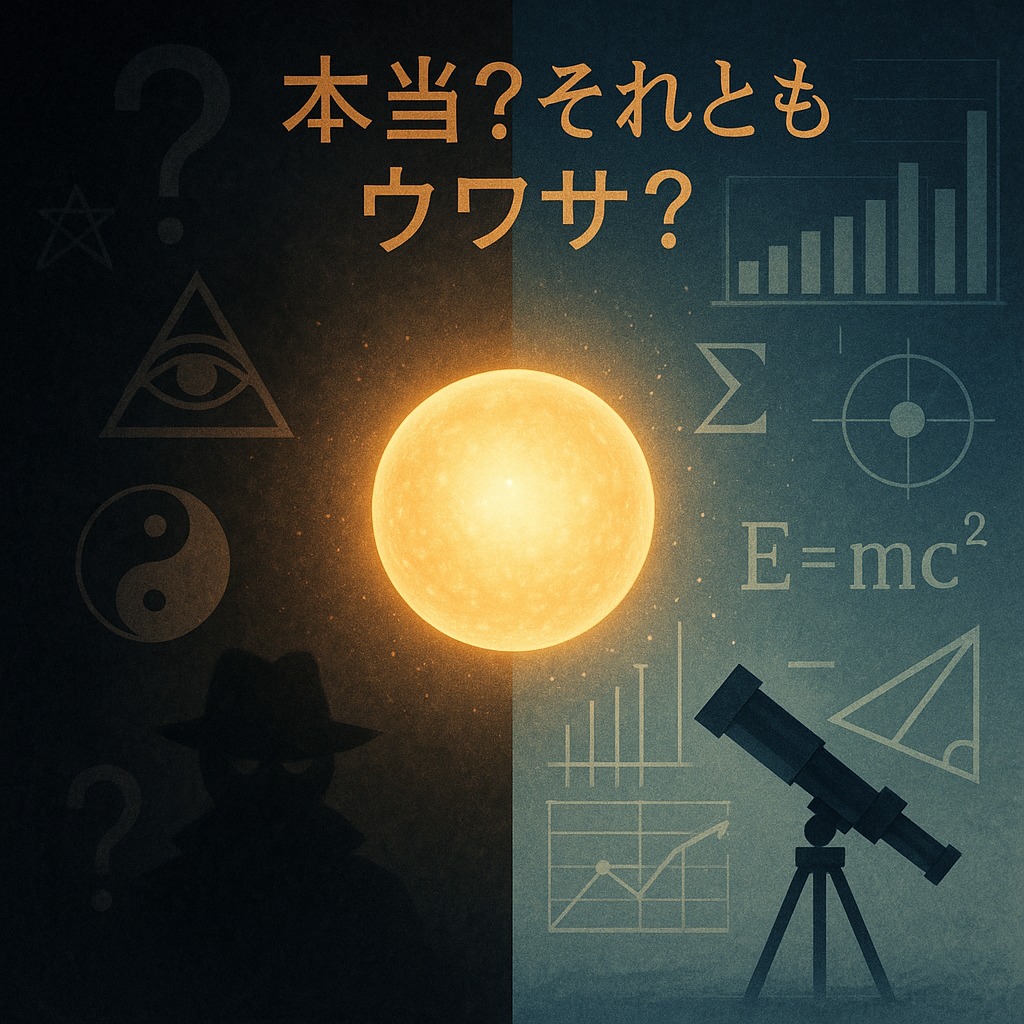夜空に浮かぶ月は、毎晩すこしずつ姿を変えていきます。
三日月、上弦の月、満月、下弦の月……この変化は何によって起こるのでしょうか?
この記事では、月の満ち欠けが起こる理由、各かたちの名称と順番、観察のポイント、生活とのつながりまでを、科学と文化の両面からやさしく解説します。
家庭での学びや自由研究のテーマとしても活用できるよう、観察や再現の方法も紹介しています。
月が光って見えるのはなぜ?
月は太陽のように自ら光を出しているわけではありません。
夜空に見えている月の光は、太陽の光を反射したものです。
太陽の光がどの面に当たっているか、そして私たちがそのどの部分を見ているか――その違いによって、月のかたちが変化して見えるのです。
この関係を図で確認したい方は、国立天文台が提供する月の満ち欠けの解説ページもおすすめです。
月の満ち欠けが起こるしくみ
月は地球のまわりを約27.3日かけて一周しています(公転)。
この間、太陽から当たる光の角度と、地球からの見え方が日々変化することで、月の形が変わって見えます。
たとえば、月が太陽と同じ方向にあるときは、光っている面が地球からは見えず、月は見えません(新月)。
反対に、月が地球の裏側にあり、太陽の光が全面に当たると、月全体が明るく見える(満月)というわけです。
つまり月の形の変化は、“見えている明るい面の割合の変化”であり、月が欠けているわけではありません。
月の形の名前と順番を覚えよう
月の満ち欠けには、それぞれに名前があります。
代表的なものを順に並べると次のようになります。
- 新月:まったく見えない月(太陽と同じ方向)
- 三日月:右下が細く光る月
- 上弦の月:右半分が光る半月
- 十三夜・十四夜:ほぼ満月に近い大きな月
- 満月:全面が光って見えるまんまるの月
- 下弦の月:左半分が光る半月
- 有明月:夜明けの空に残る細い月
これらの形は約29.5日で一巡します。この周期は「朔望月(さくぼうげつ)」と呼ばれ、旧暦や季節行事とも深く関わっています。
月にまつわる呼び名や異名については、月の名前・異名・和名を学ぶ記事で詳しく紹介しています。
月齢と観察に最適なタイミング
月齢とは、新月からの日数を表したものです。
月齢によって、月が出る時間や方角が変わります。
- 月齢3:夕方、西の空に見える三日月
- 月齢7〜8:夜に南の空に見える上弦の月
- 月齢15:夕方に東から昇る満月
- 月齢22〜24:明け方の空に見える下弦の月
月の出る時刻や方角、月齢カレンダーを知りたいときは、国立天文台の「こよみのページ」が便利です。
観察を記録してみよう
満ち欠けは毎日少しずつ変化していきます。
定期的に観察してスケッチを描いたり、スマホで写真を撮って並べたりすれば、科学的な理解とともに記録としての価値も生まれます。
・形(どちらが光っているか)
・大きさの変化
・出てくる時間帯や方角
こうした記録は、家庭学習にも自由研究にも活用できます。
観察に便利な望遠鏡やスマホ撮影の方法は、スマホ撮影できる望遠鏡まとめで紹介しています。
月の満ち欠けを体験で理解する
理論だけでなく、実際に手を使って満ち欠けを再現してみると、理解がより深まります。
懐中電灯を「太陽」、ピンポン玉を「月」、自分の目を「地球」に見立てて、
部屋を暗くしてボールを懐中電灯のまわりで回してみてください。
どの向きで、月のどの部分が光って見えるか――
自分の目で体験すれば、「なるほど!」という納得が自然と生まれます。
満ち欠けのある暮らし
昔の人々は、月の形を見て季節を知り、祭りの日取りを決め、農作業の予定を立てていました。
旧暦では、新月を「一日(ついたち)」とし、満月を十五夜、十三夜などと呼んでいました。
今も残る行事や言葉から、月はただの天体ではなく、人の生活と文化のリズムに深く関わっていた存在であることがわかります。
月の文化や言葉については、月の名前・異名・和名を学ぼうも参考にしてください。
月のある空間を楽しむ:TOOGE月ライトの紹介
夜空を見上げて月を観察したあと、部屋でも月を感じられるアイテムがあると、日常の中に自然と学びが生まれます。
TOOGEの「月ライト」は、3Dプリントで再現されたリアルな月のランプ。
リモコン・タッチ操作で3色調光でき、タイマー機能もついています。観察のあと、寝室の明かりを“月色”に変えるだけでも、心地よい記憶が残ります。
プレゼントにも人気で、暮らしの中に“本物そっくりの月”を取り入れたい方にぴったりのアイテムです。
TOOGE 間接照明 おしゃれ プレゼント 女性 人気 月ライト【4代目】 3Dプリント usb充電 タッチ調光 無段階…
【おやこトークタイム!】満ち欠けを伝えるときのヒント
月の満ち欠けを説明するとき、「見えなくなるのは消えているわけじゃない」ということを伝えるのがポイントです。
たとえばこう伝えてみてください。
「月はいつも丸いけど、太陽の光が当たるところだけが光って見えてるんだよ」
「光が当たってても、こっちからは見えないときもあるんだよ」
このような声かけから、自然に“見え方と構造”をつなげて理解できるようになります。
模型を使ったり、ライトを使って実演してみたり、TOOGE月ライトを見ながら話すのもおすすめです。
まとめ
月の満ち欠けは、太陽・地球・月の位置関係という“宇宙の動き”によって生まれています。
毎日の小さな変化を追いかけるだけで、空の見え方が少し変わってきます。
・月は太陽の光を反射して見えている
・満ち欠けは見える部分の変化によるもの
・29.5日周期でかたちが一巡する
・観察と記録は学びの入り口に
・文化や言葉とも深く結びついている
知識としてだけでなく、生活の中で自然と感じられる月のリズム。
空を見上げるたびに、「今日はどんな月?」と問いかける習慣が、未来への知的好奇心を育ててくれます。