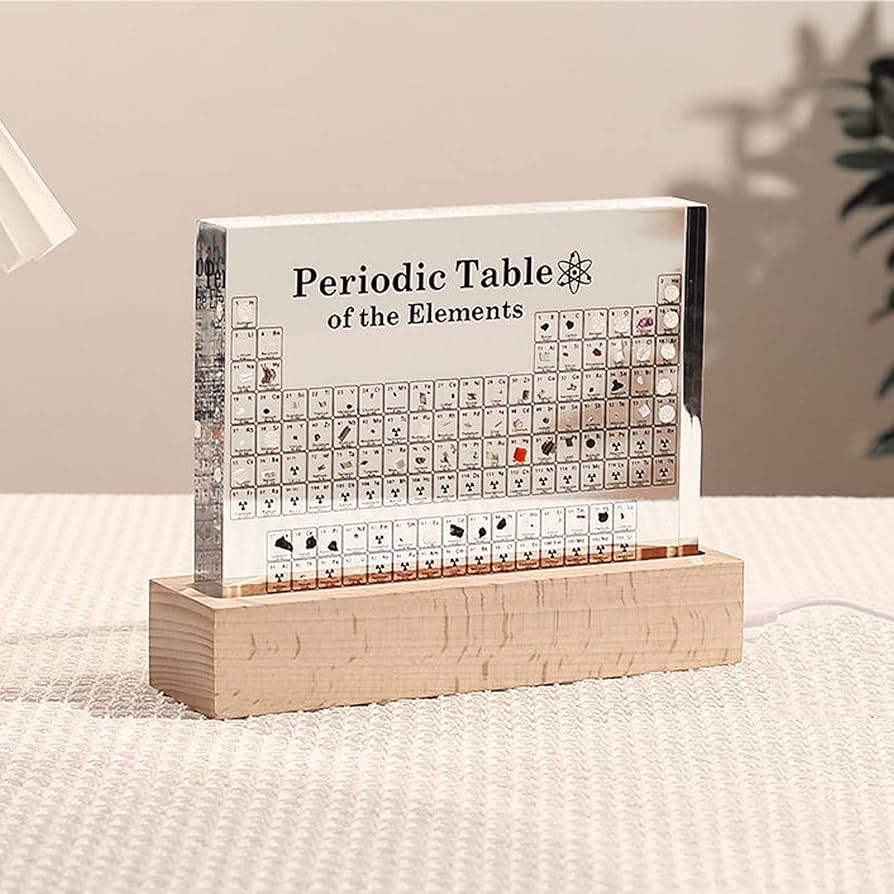「今日は変な夢を見た!」と目覚めたときにはっきり覚えていても、
朝ごはんのあとにはスッキリ忘れてしまっていることってありませんか?
夢の記憶はとても不思議です。はっきり思い出せることもあれば、まるで最初から見ていなかったかのように消えてしまうこともあります。
この記事では「夢を覚えている理由」と「忘れてしまう理由」を、脳や睡眠のしくみとあわせてわかりやすく解説します。
前回の記事「潜在意識と夢の関係」とあわせて読むと、より深く理解できます。
夢を覚えていられるのはなぜ?
夢を覚えている人にはいくつかの共通点があります。
- レム睡眠の終わりごろに目が覚める
- 夢に**強い感情(恐怖・驚き・喜びなど)**が伴っている
- 夢を覚えておきたいという意識が強い(夢日記をつけている など)
実は夢の記憶は、目覚めた直後の行動に左右されることが多いのです。
起きた直後に布団の中で少し思い返すと、記憶が定着しやすくなります。
なぜ夢はすぐに忘れてしまうの?

科学的には、夢が忘れやすい理由には次のような仮説があります。
・記憶の中枢が「オフ」になっている
夢を見ているとき、**記憶を司る「海馬」**の働きは低下しています。
そのため、夢の内容は短期記憶にしか残らず、すぐに消えてしまうのです。
・脳が「現実ではない」と判断している
夢はリアルに感じられても、脳にとっては「現実の出来事」ではありません。
そのため、不要な情報として削除されるという説もあります。
・起きてすぐに別のことを考えると消える
起きてすぐスマホを見たり、会話を始めたりすると、夢の記憶が上書きされやすくなります。
記憶の定着には“余韻”が必要なのです。
夢を見る回数と記憶の関係
私たちは一晩に4〜5回、夢を見ているとされます。
でも実際に覚えている夢はごく一部。
覚えている夢が多い人は、次のような傾向があるといわれています。
- 睡眠が浅い(レム睡眠が多い)
- 感受性が強い
- 日中のストレスが多い
- 寝起きがスムーズで意識が切れにくい
夢の記憶と感情には深い結びつきがあります。
このしくみについては「夢とレム睡眠の関係」でも解説しています。
記憶の整理と夢の関係
睡眠中、脳は**「記憶の整理整頓」**をしていると考えられています。
- レム睡眠:感情や体験の“再生”と再構築
- ノンレム睡眠:重要な記憶の“固定化”と長期保存
夢の内容がバラバラに見えるのは、記憶の断片を組み合わせて処理しているからなのです。
親子トークタイム!子どもにこう話してみよう
「夢って、寝てるあいだに脳が思い出の片づけをしてるときに見えるんだって。でも片づけ途中だから、すぐ忘れちゃうんだよ。もしすごく楽しかった夢があったら、朝起きてすぐに『こんな夢見た!』って話すと、覚えていられやすくなるよ!」
まとめ
- 夢を覚えていられるのは、レム睡眠の終わりに目覚めたときや感情が強いとき
- 忘れてしまうのは、脳の記憶中枢が働いていないから
- 夢の記憶は、目覚めてすぐの行動に大きく左右される
- 覚えておきたいなら「思い返す」「書く」「話す」がおすすめ
夢の記憶をたどることは、心の奥にある気持ちと向き合うことでもあります。
今日からあなたも、夢の“探偵”になってみませんか?