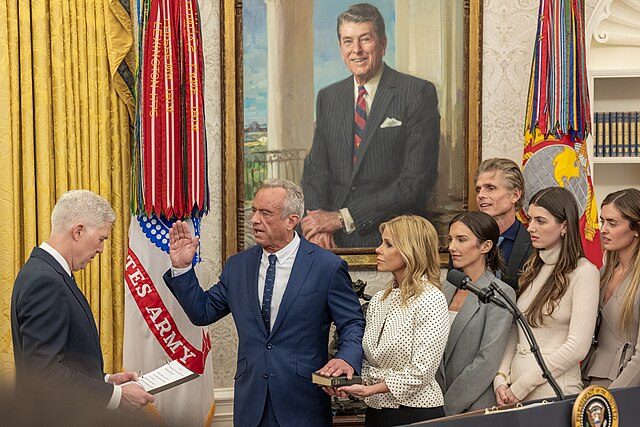2025年、トランプ前大統領が再び「相互関税」を軸とした貿易戦略を掲げ、大統領選の争点の一つになっています。注目すべきはその強硬な政策だけでなく、「そもそも誰が関税を決めるのか?」という制度的な対立の構図です。
米議会では、大統領の“単独関税権限”に対して、「歯止めをかけるべきだ」という声が再び強まっています。本記事では、アメリカの通商制度の仕組みと、議会と大統領のせめぎ合いを解説します。
アメリカの関税制度と「大統領の権限」
アメリカでは本来、通商政策を決める権限は議会(連邦議会)にあります。しかし、いくつかの法律によって、大統領が単独で関税を設定できる場面もあります。
代表的なものには以下の3つがあります。
- 通商拡大法232条:国家安全保障を理由に関税を課すことができる。トランプ政権時代、鉄鋼・アルミ製品への関税で使用。
- 通商法301条:他国の不公正な貿易慣行に対して報復措置を取れる。主に対中国の制裁関税に使われた。
- 国際緊急経済権限法(IEEPA):非常事態時に経済制裁を発動できる大統領権限。
これらにより、議会の事前承認がなくても関税が実施されるケースがあるのです。
議会の反発:「チェック機能を取り戻せ」
2025年4月現在、アメリカ議会ではトランプ氏の「再び単独で関税を決めようとする動き」に対して、超党派で警戒が高まっています。
民主党の上院議員は「通商政策の透明性と民主的手続きを回復させるべき」として、大統領の関税権限を制限する法案を提出する構えを見せています。
共和党内でも「議会軽視への不安」が一部で共有されており、2018年〜2020年に起きた“通商独走”への反省から、議会回帰の気運が再燃しているのです。
通商政策をめぐる今後の焦点
通商政策は外交と経済の交差点にあります。関税が誰によってどのように決定されるかによって、貿易の流れや各国との関係が大きく左右されます。
今後の注目点は次のとおりです:
- 6月に予定されているアメリカの報復関税発動が、議会の介入で止まる可能性があるか
- トランプ氏が当選した場合でも、議会が関税発動を制限できる仕組みが作られるか
- 超党派による「関税審査法案(仮)」が実現するか
関連リンク
トランプ氏の新・相互関税案とは何か?
なぜEUは「報復関税」を延期したのか?
親子トークタイム|子どもにこう話してみよう
「アメリカでは、国のリーダー(大統領)が“外国から入ってくるものにかけるお金=関税”を1人で決められるルールがあるんだ。でも、“国会”みたいな場所(議会)の人たちは、『本当にそれでいいの?みんなで決めようよ』って言ってるんだよ。」
「大事なことを、1人だけで決めてしまわないように、見張る人たちがいるって大切なことだよね。」
このテーマは、子どもにとっても「ルールの決め方」「権力のバランス」を考えるきっかけになります。
まとめ:手続きのルールが変われば、世界も変わる
相互関税のような強い通商政策が再び浮上する中で、「それを誰が、どのように決めるのか」という制度的なルールがあらためて問われています。
アメリカの大統領と議会のバランスは、アメリカ国内だけでなく、世界経済の安定にも直結します。通商政策の“中身”だけでなく、“仕組み”にも目を向けることで、より深く国際政治・経済を理解できるようになるはずです。