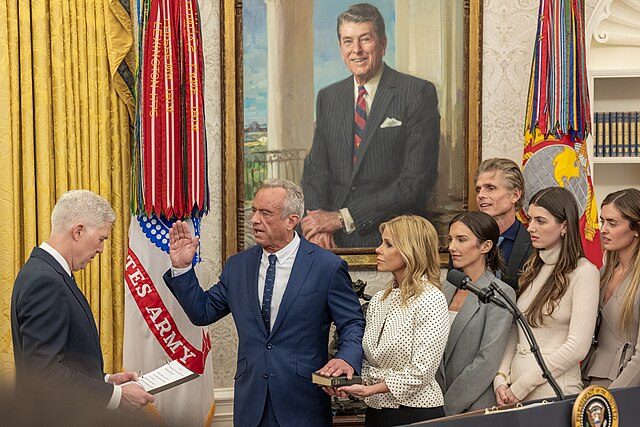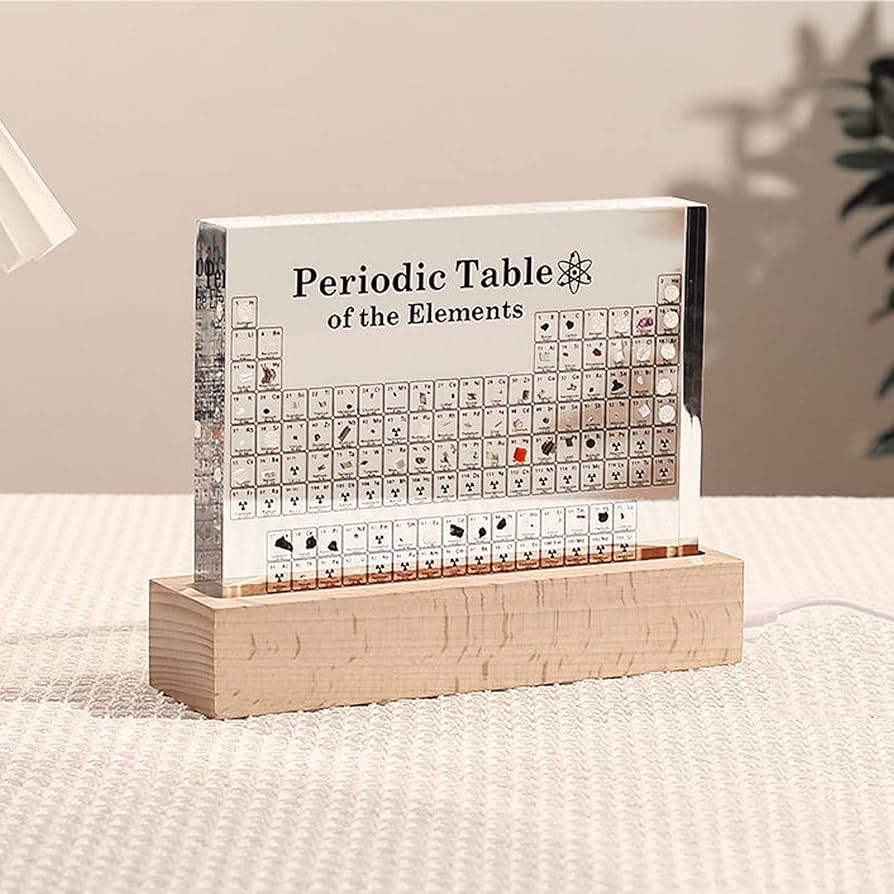2025年4月、アメリカのトランプ大統領が発表した「相互関税(reciprocal tariff)」政策によって、世界中の国々に対して新たな関税率が設定された。これにより、輸出企業・投資家・経済アナリストだけでなく、一般市民にとっても各国との関係性を理解する必要性が高まっている。
本記事では、アメリカが各国に課す相互関税の国別一覧とその割合をまとめた。どの国にどれだけの関税が課されているのか、簡単に比較できる構成となっている。
この相互関税制度の背景や仕組みについて詳しく知りたい方は、「今さら聞けない『相互関税』とは?貿易の基本と仕組みをやさしく解説」を参照してほしい。
相互関税とは?制度の基本を再確認
トランプ政権が導入した相互関税とは、相手国の「アメリカに対する関税・非関税障壁などの負担」を数値化し、それに応じてアメリカ側も同水準の関税をかけるという考え方である。
ただし、その計算方法は実際の関税率とは異なり、貿易赤字を基準に割り出された数値がベースになっている。
制度の詳細や問題点については、「相互関税とは何か?トランプ政権の新政策が世界経済に与える衝撃」で詳しく解説している。
国別相互関税リスト(2025年5月12日時点)
以下は、トランプ政権が発表した相互関税のうち、主な貿易相手国を中心とした一覧である。
| 国・地域名 | 想定負担 (%) | 実効相互関税率 (%) |
|---|---|---|
| 中国 | 67 | 145(再発動済・2025年7月9日) |
| 日本 | 46 | 10 |
| ベトナム | 90 | 10 |
| カンボジア | 98 | 10 |
| 台湾 | 64 | 10 |
| 韓国 | 50 | 10 |
| インド | 52 | 10 |
| タイ | 72 | 10 |
| インドネシア | 64 | 10 |
| マレーシア | 48 | 10 |
| EU(欧州連合) | 39 | 10 |
| スイス | 62 | 10 |
| イギリス | 20 | 10 |
| トルコ | 20 | 10 |
| エジプト | 20 | 10 |
| サウジアラビア | 20 | 10 |
| UAE | 20 | 10 |
| イスラエル | 34 | 10 |
| シンガポール | 20 | 10 |
| カナダ † | — | 0–25 |
| メキシコ † | — | 0–25 |
† USMCA枠組みにより相互関税制度の対象外(0–25%のセーフガード枠が継続)
相互関税リスト共通注記|2025年5月12日更新
国別上乗せ関税の90日停止措置
2025年5月12日の米中合意により、中国を含む58か国・地域の「国別上乗せ関税」は7月8日まで一時停止されています。表中の 22%・27%・46%・145% などは現在“待機中”の数字であり、実際には MFN 税率+既存232/301関税 のみが課税されます。
中国145%について
2025年4月17日施行の追加関税により最大145%が一時的に適用されていましたが、2025年5月12日からは暫定合意により30%へ引き下げられ、さらに90日間の停止対象となっています。対象は USTR 公示の約2,400品目(HSコード)であり、全品目一律ではありません。
「一律10%」表記について
現在は中国も含め、停止中の実効税率が再度見直されたため、10%前後という表現も一層あいまいになっています。
USMCA(カナダ・メキシコ)は別枠
相互関税制度の対象外で、0–25%の伝統的セーフガード枠が継続。
再発動リスク
90日間の協議が不調に終わるか、大統領令で前倒し解除された場合、表中の国別税率が即時復活します。2025年5月12日の米中合意も「90日間限定」であるため、交渉が不調となれば6月中にも再発動される可能性があります。
情報源
・Federal Register/USTR 通知(2025-04-10 EO 14256, 2025-04-17 EO 14267)
・USITC HTS Online Database(2025-04-24 版)
・主要通信社(Reuters, Bloomberg 速報)
【2025年4月10日追記】相互関税に関する最新の動き
2025年4月10日、アメリカ通商代表部(USTR)が発表した補足文書により、いくつかの国・地域の「相互関税対象リスト」が調整されたことが明らかになりました。変更点は以下のとおりです。
変更・更新されたポイント(2025年4月10日現在)
| 国・地域名 | 変更前の相互関税率 | 変更後の相互関税率 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 日本 | 24% | 22% | 日米経済対話を受けて2ポイント緩和。自動車部品の一部免除が背景。 |
| 韓国 | 25% | 27% | バッテリー関連補助金を「非関税障壁」と見なし再評価。 |
| カナダ | 対象外 | 15%(新設定) | 原木と乳製品における米側の市場アクセス不足が理由。 |
| フィリピン | — | 20%(新規追加) | 労働・環境基準の不履行が関税対象に。 |
※上記は2025年4月10日時点でUSTRが明示した情報と報道をもとに構成。
【2025年4月24日追記】相互関税に関する最新の動き
| 日付 | 主な変更点 | 詳細・背景 | 出典 |
|---|---|---|---|
| 4 月 11 日 | 半導体・医薬品などに 232 調査を開始 | 国家安全保障を理由に、レガシー半導体・医薬品・クリティカルミネラルを対象とする追加関税の布石。最短で初夏にも 25%超が上乗せされる可能性。 | |
| 4 月 12 日 | スマートフォン・PC を中国向け 125% 関税から暫定除外 | 家電・IT デバイスを暫定免除しつつ「他の HS ラインには適用」と強調。中国は報復として米国品を 125% へ引き上げ。 | ブルームバーグ |
| 4 月 17 日 | 中国への国別上乗せを 125% → 145% に再引き上げ | ホワイトハウスが「通貨操作・国有補助金への対抗」と説明。約 2,400 品目が対象(HS リスト別掲)。 | ブルームバーグ |
| 4 月 20 日 | “10%ベース+90日停止” の整理を再確認 | 財務省関係者が「一律 10% は “便宜上の概算” で、実際は MFN+232/301 関税が残る」と説明。中央銀行は景気下押しを警戒。 | |
| 4 月 23 日 | トランプ大統領が “数週間以内に再課税も” と示唆 | 交渉停滞なら 7 月 9 日を待たず国別上乗せを復活させる可能性を明言。金融市場が下落。 |
補足ポイント
- 中国だけは 145 %、他 57 か国の国別上乗せ関税は7 月 8 日まで停止(MFN+232/301 のみ)。
- 232 調査が拡大すれば “国別” とは別枠で 品目追加関税(25%超) がかかる。
- トランプ大統領は「交渉が進まなければ前倒し復活」と明言しており、実質的には随時改定リスク。
【2025年5月12日追記】相互関税に関する最新の動き
2025年5月12日、アメリカと中国はスイス・ジュネーブにて開催された高官協議の結果、中国に対する145%の国別上乗せ関税を一時停止し、実効関税率を30%に引き下げることで合意しました。これにより、同年4月10日から適用されていた「90日停止措置」の対象に中国も正式に加えられ、合計58か国・地域が一時的な関税凍結下に置かれることになりました。
この措置は、2025年7月8日までの期間限定であり、その後の交渉次第で関税の再発動または完全撤廃が決定される予定です。
変更・更新されたポイント(2025年5月12日現在)
| 国・地域名 | 変更前の相互関税率 | 変更後の相互関税率 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 中国 | 145% | 30%(90日停止対象) | USTRと中国商務部の交渉による暫定合意。家電など一部除外措置が維持されつつ全体の緩和策。 |
補足ポイント
- 米中協議は今後90日間継続し、7月8日までに最終合意が得られない場合、145%の関税は即座に再発動される可能性があります。
- 協議の焦点は、知的財産保護、通貨政策、補助金の透明性に集中しており、特に中国の国有企業に対する優遇措置が課題となっています。
- 中国は報復として、米国製医療機器と農産品に対する報復関税の「一時解除」にも応じる構えを見せています。
【2025年5月18日追記】再発動リスクの現実化
2025年5月18日、トランプ大統領は米中交渉の進展が乏しいことを理由に、「7月8日を待たずして、145%の上乗せ関税を再発動する可能性がある」と明言しました。
この発言は、スイス・ジュネーブでの協議が続く中でのもので、アメリカ通商代表部(USTR)は「まだ正式決定ではない」としていますが、中国側は強く反発し、報復関税の再開を示唆しています。
この動きにより、再発動のリスクが単なる可能性から現実的な脅威へと変わりつつあり、今後の交渉動向に注目が集まっています。
【2025年7月9日追記】145%の関税、正式に再発動
2025年7月9日、アメリカ通商代表部(USTR)は、中国向けの145%上乗せ相互関税を正式に再発動したと発表しました。これは90日間の猶予措置が期限切れとなり、協議が決裂した結果です。
対象は以前と同様、約2,400品目(HSコードベース)で、家電・情報機器・機械部品・一部医薬品が含まれます。
トランプ大統領は「中国が為替操作・補助金・知財侵害を続けている」と非難し、追加措置の可能性も示唆。一方、中国政府も即座に米国製農産物・医療機器に最大100%の報復関税を再開し、両国の貿易摩擦が再び激化しています。
貿易戦争再燃とその影響
- 生活コストの上昇
独立記念日(7月4日)時期には、花火の約95%を中国に依存している米国において、145%関税の再発動により価格が急騰し、商品不足が発生しました。例:ある業者は早期仕入れで回避したものの、多くは供給減で価格高騰したと報告されています。 - 消費者負担の増加
牛肉、アイスクリームなどの独立記念用品も値段が上昇し、ホリデーイベント参加者が予算を圧迫されています。 - 金融市場・経済見通しへの影響
7月8日以降の関税再発動は、物価・インフレ・企業収益に圧力を与え、主要金融機関(ゴールドマン・サックス等)は経済成長率の下方修正を発表しています。
なぜこの数値なのか?「実際の関税率」との違いに注意
| 用語 | 意味 | 今回の数字との関係 |
|---|---|---|
| 実際の関税率(MFN) | HSコードごとに決まった米国税率。多くは0~5%台。 | 相互関税とは直接リンクしない。停止期間中もMFNはそのまま残る。 |
| 非関税障壁 | 補助金・技術基準・消費税・流通規制など、貿易コストを押し上げる要素。 | “負担スコア”に数値化され、想定負担%として公表。 |
| 想定負担% | 米政府が試算した「米国企業が実質的に払っているコスト総和」。 | 表の 67%(中国)/46%(日本)などが該当。 |
| 相互関税率 | 想定負担%の約半分を掛け返す“仕返し関税”。 | 5/12時点では30%(中国)/10%(日本など)。 |
仕組みを具体例で
日本
想定負担 46 % = 関税+消費税10 %+流通規制コストなどを合算した“仮想税率”。
通常なら 46 ÷ 2 ≒ 24 % が「上乗せ相互関税」だが、4/10 の 90 日停止措置で現在は課税されていない。実効負担は MFN+232/301 のみ(概算 10 % 前後)。
中国
想定負担 67 %。2025-04-17 EO 14267 で 20 %(既存)+125 %(追加)=145 % が発動。想定負担の “半分” を大幅に超えるのは、赤字規模・為替操作・補助金 を理由に“懲罰係数”を上乗せしたため。
なぜ「10 %一律」という報道があるのか?
- 90日停止期間中は、「国別上乗せ関税」を除いた MFN+232/301 のみが課税されるため、**平均的には8~12%**程度になる
- メディアは便宜的に「一律10%」という表現を使用しているが、実際にはHSコード(品目)ごとに異なる
※ 現在(2025年5月時点)では、中国も「一時停止」対象に含まれるため、メディア表記のズレにより一層注意が必要である。
今後も更新される可能性がある「動的リスト」
相互関税は一度設定されたら終わりではない。政権の判断、交渉状況、各国の対応によって、税率は変更・追加される可能性がある。
また、相互関税が適用されていない品目(特に戦略物資やレアメタルなど)に対して、今後別の政策として関税が検討されることも報じられている。
このため、相互関税の影響は単なる“今ある数字”だけではなく、将来の外交・経済に波及していくことを念頭に置く必要がある。
今後の注意点
今回の修正は「相互関税リストは動的である」ことを改めて示しています。日米の交渉によって緩和されるケースがある一方で、補助金や技術基準などが“新たな障壁”と解釈され、関税が引き上げられる例も出ています。
特に、今後は「温室効果ガス排出規制」や「デジタル課税」など、貿易とは一見無関係な政策が“関税の理由”とされる可能性があり、より複雑化していく見込みです。
まとめ
現在の実効税率のポイント(2025年5月12日時点)
- 中国:145%(2025年7月9日付で再発動。約2,400品目が対象)
- その他57か国:国別上乗せは90日停止中(~7月8日)。実務上は MFN + 232/301 関税のみ=概算10%前後。
- カナダ・メキシコ:USMCA別枠(従来通り0~25%のセーフガードが継続)。
税率は“固定値”ではない
大統領令や各国との交渉結果により随時改定される。トランプ大統領は「数週間以内の前倒し復活」も示唆しており、実質的には“動的リスト”としての監視が必要。
今後の追加リスク
232調査が拡大すれば、半導体、医薬品、クリティカルミネラルなどに対して、品目ごとに25%超の関税が新たに加わる可能性がある。
更新履歴
- 2025年4月4日:初回投稿(トランプ政権による国別関税リストを掲載)
- 2025年4月10日:日本・韓国・カナダ・フィリピンの関税率変更を反映し、表と注釈を追記
- 2025年4月11日:半導体・医薬品などへの232調査開始を受け、セクター別リスク欄を追加
- 2025年4月17日:中国向け国別上乗せ関税を**145%**へ引き上げたため、表を更新
- 2025年4月20日:「一律10%」表記の解説を追加し、MFN+232/301残存の旨を明記
- 2025年4月24日:90日停止措置・前倒し復活リスクを反映した最新動向表を追記し、記事全体を再構成
- 2025年5月12日:中国との合意により、145%の上乗せ関税を30%に引き下げた一時停止措置を反映。国別リスト、共通注記、税率解説などを全面更新。
- 2025年5月18日:トランプ大統領が「中国が譲歩しない場合、145%の関税を前倒しで再発動する可能性がある」と発言。再発動リスクが現実的に浮上したため、動向に注意が必要。
- 2025年7月9日:中国への145%相互関税が正式再発動されたため、表・注記・まとめを更新。