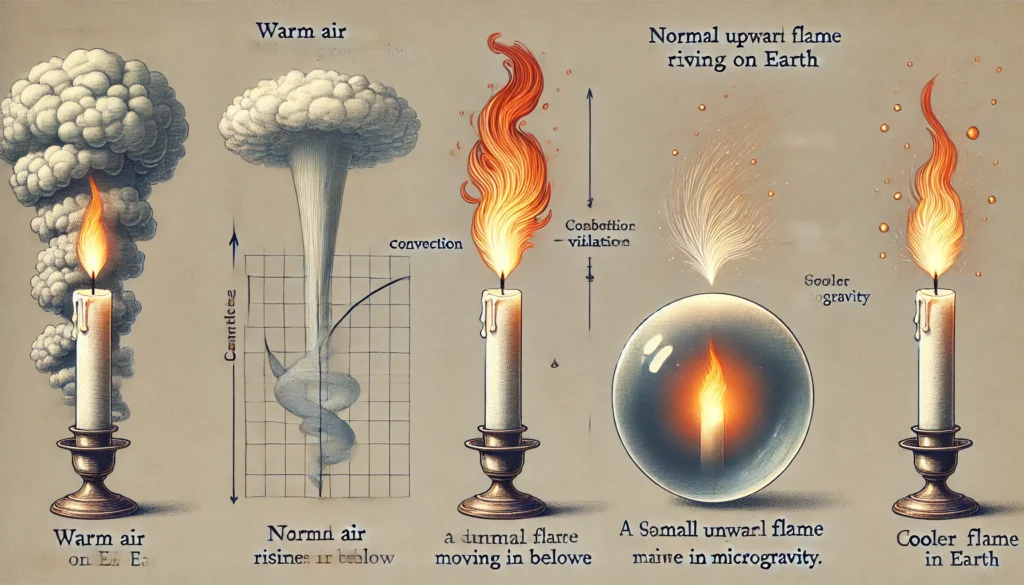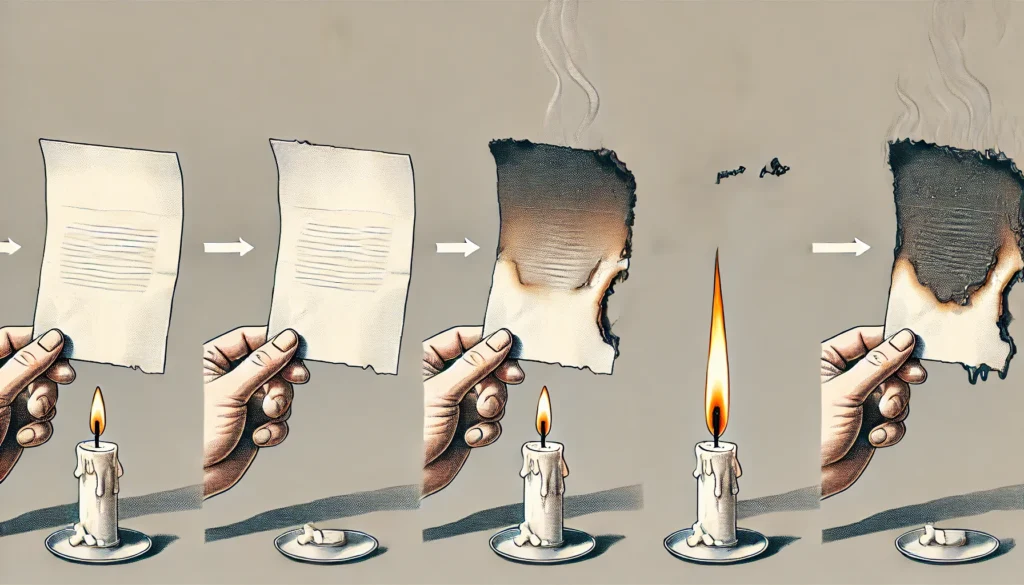「現場に残された指紋から犯人を特定!」
ドラマやアニメでよく見かけるシーンですが、実際の警察も本当にそんな方法で犯人を見つけているのでしょうか?
この記事では、警察がどんな道具を使って指紋を採取しているのか、どうやって人と一致させるのかなど、現実の捜査で使われている指紋鑑定の仕組みを、子どもにもわかるように解説します。
指紋がなぜ捜査に使われるの?
私たちの指には、指紋と呼ばれる線の模様があります。
この模様は一人ひとり違っていて、一生変わらないという特徴があります。
そのため、現場に残された指紋が「その人だけの証拠」になるのです。
犯人が何かに触れたとき、皮脂や汗が残って「指紋のあと」になります。これを見つけて、記録し、比較することで、警察は事件の手がかりを得ています。
警察はどうやって指紋を見つけるの?
警察は、目に見えない指紋もいろいろな方法で浮かび上がらせることができます。
1. アルミニウム粉(粉末法)
もっとも一般的な方法です。
物の表面に細かいアルミニウムの粉をふりかけ、ブラシで軽くなでると、指紋の脂にだけ粉がくっついて模様が見えてきます。
見つけた指紋は、セロハンなどのシートでそのままはがして保存します。
2. 瞬間接着剤(シアノアクリレート法)
つるつるしたプラスチックや金属の表面に有効な方法です。
密閉容器に物を入れ、瞬間接着剤の蒸気を充満させると、指紋にだけ白くくっきりと反応が出てきます。
3. 蛍光・紫外線ライト
見えにくい場所には、ブラックライトを使って指紋を光らせる方法もあります。薬品と組み合わせて行うと、暗い中でもくっきり確認できます。
4. 化学薬品による検出
紙や布など吸収性のある素材には、薬品をしみこませることで反応させて指紋を可視化します。
こうして、見えない指紋を「目に見える形」にしていくのが“採取”の第一歩です。
採取された指紋はどうなる?
見つけた指紋は、保存されたのち、警察のデータベースにある他の指紋と照合されます。
このとき使われるのが「AFIS(自動指紋識別システム)」というコンピュータです。
日本では警察庁が全国の指紋を管理し、次のようなケースに照合します。
- 事件現場の指紋と、過去の前科者の指紋を比較
- 入国管理や出入国審査(出入国管理庁)との照合
- 免許証や住民基本台帳の本人確認など
この照合で一致すれば、「誰の指紋か」がわかり、捜査の重要な手がかりになります。
どんなものに指紋は残る?
指紋は、表面がなめらかなものほど残りやすいと言われています。たとえば:
- コップ・グラス
- ドアノブ
- 窓ガラス
- スマートフォン
- 包丁などの金属
ただし、水にぬれたり布に触ったりすると、すぐに消えてしまうこともあるため、早い段階での採取がカギになります。
子どもでも指紋採取はできる?
実は、警察と同じような方法で指紋を採取できるキットが市販されています。
親子で実際にやってみたい人には、こんなキットがおすすめです。
🔍 本格的に体験できる!
学研 動画でわかる! 自由研究おたすけキット 指紋を調べよう(対象年齢:小学3年生以上)30×118×195mm J750858
このキットには、警察が使うのと同じようなアルミ粉や透明シート、ガイドブックが入っており、家庭で本格的な指紋採取体験ができます。
自由研究のテーマにもぴったりです。
【おやこトークタイム!】子どもに伝える方法
子どもは「警察ってかっこいい!」「犯人を見つけたい!」という興味を持つもの。
でも、それだけでなく、「証拠ってどうやって集めるの?」「間違いはないの?」という問いを一緒に考えることが大切です。
子どもにこう話してみよう
テレビで警察が「現場に指紋が残ってたぞ!」って言ってるよね?
実はあれ、本当にやってることなんだよ。
指の脂が、触ったものにちょっとずつついて、見えない模様として残るんだ。
それを粉やライトで見えるようにして、誰の指紋かを調べるんだよ。
やってみたい?キットで体験もできるよ!
まとめ
- 指紋は一人ひとり違い、一生変わらないため、捜査に使われる
- 警察はアルミ粉・薬品・ライトなどで指紋を浮かび上がらせて採取する
- 採取された指紋はデータベースと照合され、人物特定の手がかりになる
- 子どもでも体験できるキットがあり、観察や自由研究にもおすすめ
- 科学と社会、そして正義について考えるきっかけになるテーマ