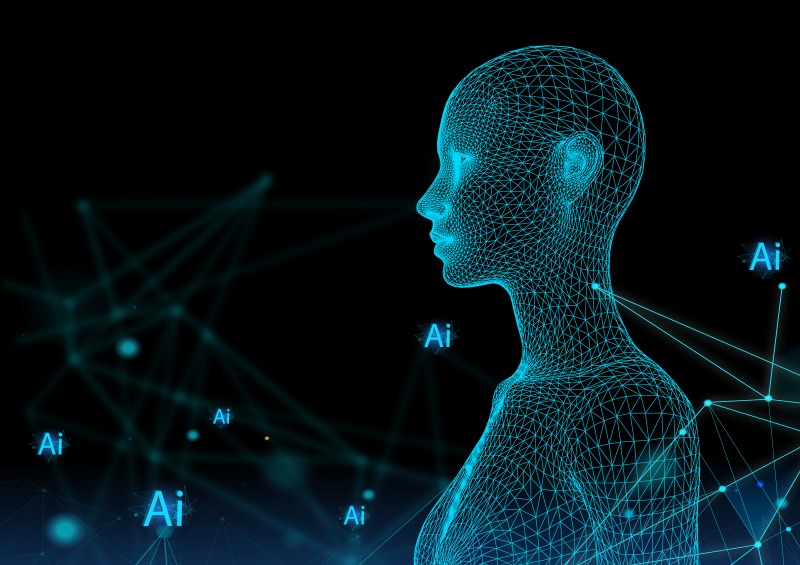「レバーを引くか、引かないか。」
このシンプルな問いから始まるトロッコ問題は、長年にわたり世界中の哲学者や倫理学者たちの思考を刺激してきました。
しかし、実はこの問題にはたくさんの派生バージョンや類似問題が存在するのをご存知でしょうか?
中には、「その選択、ほんとうにフェア?」と考えさせられるものから、「なぜそんな設定に…?」とクスッと笑ってしまうようなパロディ風のものまで。
本記事では、トロッコ問題の代表的なバリエーションや派生シナリオを紹介しながら、それぞれがどんな問いを投げかけているのかをやさしく解説します。
トロッコ問題の基本的な構造や倫理的な背景について知りたい方は、こちらの記事もあわせてご覧ください。
太った人を突き落とす問題(橋の上のバージョン)

もっとも有名な派生バージョンが、「太った人を橋から突き落とす」というシナリオです。
問題の内容
線路の上に5人がいて、トロッコが猛スピードで迫っている。
橋の上からそれを見ているあなたの隣には、体格の大きな男性が立っている。
もしその人を橋の上から突き落とせば、トロッコはその身体にぶつかって止まり、5人は助かる。
でも、その1人は確実に命を落とす。
あなたはその人を突き落とすべきか?
倫理的なポイント
このバージョンでは、「レバーを引く」という間接的な行為ではなく、「人を自分の手で押す」という直接的な加害行為が求められます。
つまり、結果は似ていても、**手段が違えば人の判断は変わるのか?**という点を試しているのです。
自分が犠牲になる問題
「他人を犠牲にするか、自分を犠牲にするか」という、より強烈な問いを投げかける派生問題もあります。
問題の内容
5人を助けるには、線路に飛び込んで自分がトロッコを止めるしかない。
あなた自身が犠牲になれば、他の人は救われる。
あなたは飛び込む?
倫理的なポイント
ここでは、自己犠牲とヒロイズムの概念が試されています。
他人に加害するのではなく、「自分を犠牲にする勇気があるか」が問われます。
このバージョンは、道徳的ヒーロー像を理想とする文化圏で強く議論されます。
脱線させる選択肢
一部の派生問題では、「レバーを引いても誰もいない線路に脱線させる」という、**“奇跡の第三案”**が用意されているケースもあります。
たとえば、
- 別の線路には誰もいないが、脱線すれば自動運転が不能になり、その後に別の大事故が起きるかもしれない。
- 切り替え先の線路には爆弾がある。
など、単純な「5 vs 1」ではない構造を取り入れて、より現実的なジレンマを再現しています。
このような問題は、AIの判断シミュレーションや、法的なモラル判断に応用されることもあります。
架空・風刺系のパロディバージョン
インターネットでは、トロッコ問題をテーマにした風刺やネタ的なバリエーションも数多く生まれています。
- 「複線ドリフト」:ありえない速度とテクニックで全員助けるというマンガ風の展開
- 「サムライが切り捨てる」:トロッコを止める役割をサムライが担う
- 「太った人が実は悪人だった」:情報があとから与えられて判断がブレる
こうした派生は真剣な議論とは一線を画しますが、「選択とは何か?」を逆説的に考えるヒントにもなります。
類似する他の倫理問題

トロッコ問題に似た構造をもつ、別の倫理問題も存在します。
カルネアデスの板
古代ローマの思想家カルネアデスによる例え話。
- 船が沈没し、2人が同じ木の板につかまっている。
- 板は1人分の重さしか支えられない。
- あなたは相手を突き落として生き残るか、それとも共に沈むか。
この話は、正当防衛と生存本能の間で倫理をどう位置づけるかを問いかけます。
医者のジレンマ
- 5人の臓器移植を待つ患者。
- 健康な1人を犠牲にすれば、5人を救える。
倫理的には完全にアウトのように思えますが、功利主義の立場では合理的です。
こうした問題も、トロッコ問題と同じように、「行為の道徳性」と「結果の善悪」がぶつかりあう構造を持っています。
親子トークタイム!子供に伝える方法
派生バージョンの多くは少し複雑で、子どもには難しく感じるかもしれません。
でも、「もしこんな場面だったら?」というストーリーとして話せば、子どもなりの想像力で受け止めてくれることが多いです。
重要なのは、「どうする?」と聞いて終わるのではなく、「どうしてそう思ったの?」と理由を聞いてあげることです。
子供にこう話してみよう!
「ある男の人が線路の近くに立っててね、その人を押すとトロッコが止まって5人が助かるんだって。
でも、その人は何もしていない。ただそこにいるだけ。
これって、やっていいと思う?」
「もしその人がすごく悪いことをしていた人だったら、どう思う?」
このように、「ちょっと複雑な話だけど考えてみる」姿勢を一緒に持つことが、子どもの思考力を育てます。
まとめ
トロッコ問題は、その派生やバリエーションによって、ますます奥深い問いを投げかけてきます。
- 「直接手を下す」 vs 「間接的な選択」
- 「自分を犠牲にする」 vs 「他人を選ぶ」
- 「判断する前に情報を与えられたら?」
こうした要素が加わることで、選択はより現実的かつ人間的なものへと変化していきます。
大切なのは、「何が正しいか?」ではなく、「なぜそう思ったか?」を繰り返し考えること。
その思考の積み重ねが、未来のAI社会や法律、教育のあり方に影響していくのです。
トロッコ問題を体験型で学びたい方は、ゲームで学ぶ記事もおすすめです。
また、自分の性格傾向を知りたい方は、トロッコ問題で性格診断してみようもぜひご覧ください。