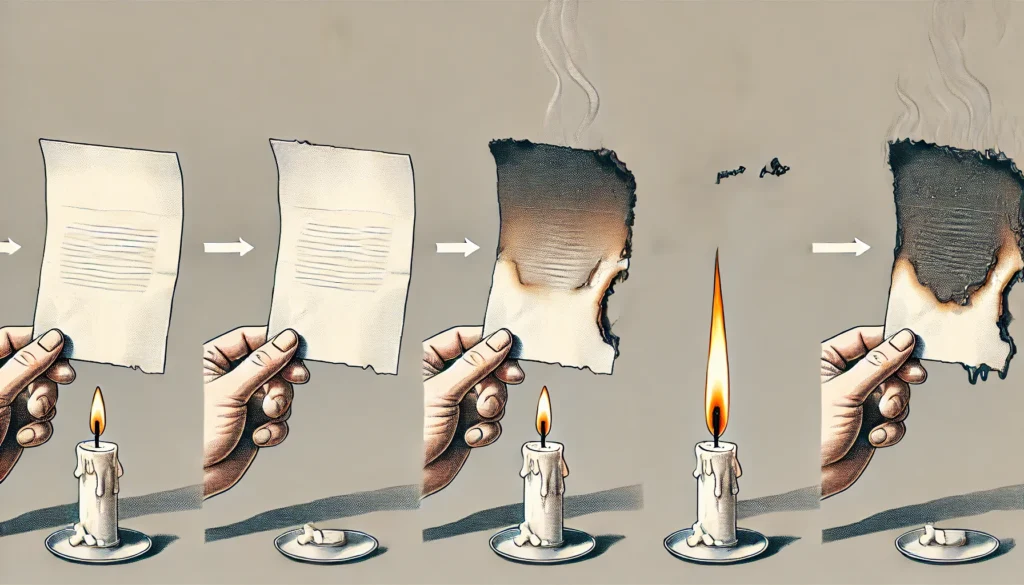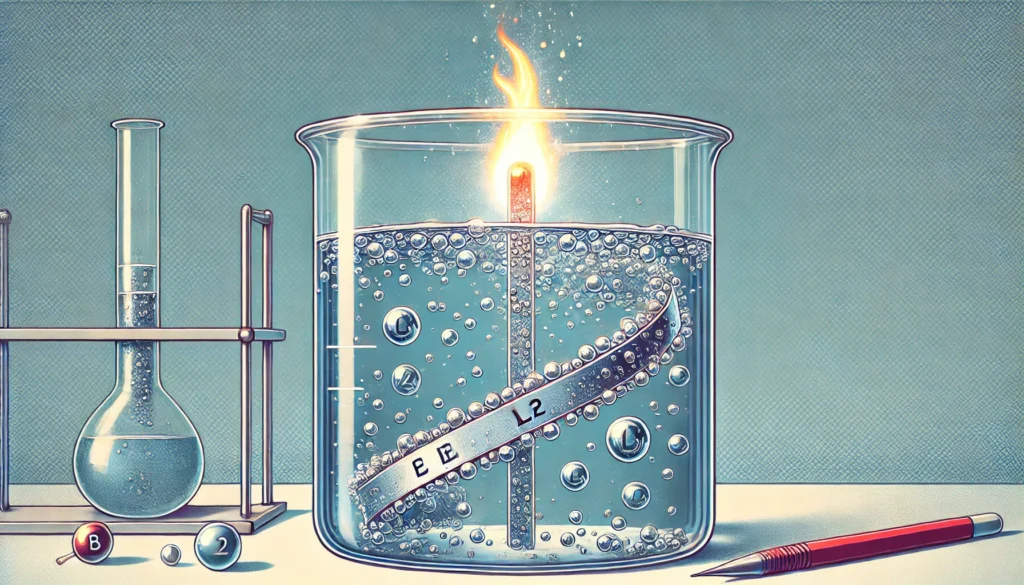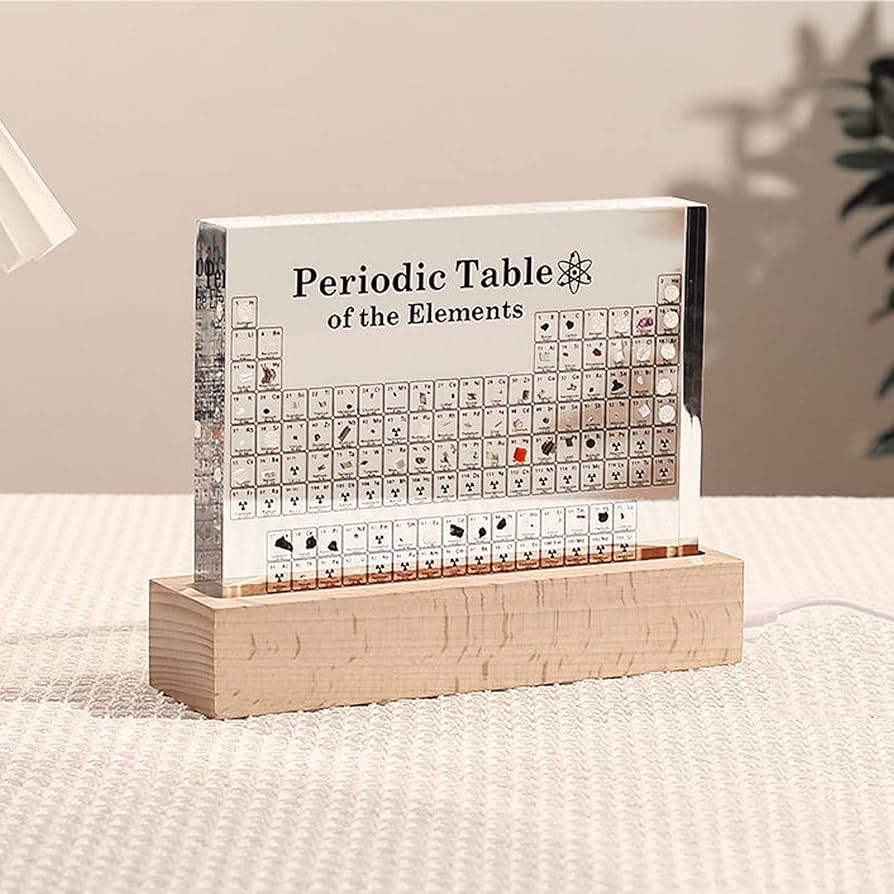「顕微鏡って、のぞくと大きく見えるけど…中はどうなってるの?」
「部品の名前がいろいろあって覚えられない!」
この記事では、顕微鏡の基本構造と各パーツの名前や役割を、小学生でもわかるようにやさしく解説します。
「スライドガラスってどっち?」「ねじってどれがどれ?」といった、授業やテストで混乱しやすいポイントもすっきり整理。
これを読めば、顕微鏡のしくみがまるっと頭に入ります。
あわせて読みたい:
👉 プレパラートってなに?顕微鏡観察の基本とおすすめセット
顕微鏡って、どうなってるの?
顕微鏡は、小さなものを大きく・はっきり見るための道具です。
そのために、レンズ・光・ピント調整のしくみが組み合わさって働いています。
全体はとてもシンプル。だけど、それぞれのパーツにはしっかり役割があります。
顕微鏡の主なパーツと役割一覧
| パーツ名 | 説明 |
|---|---|
| 接眼レンズ | のぞく部分。ここから観察します |
| 対物レンズ | プレパラートの上にある拡大レンズ |
| レボルバー | 対物レンズを切り替える回転部分 |
| ステージ | プレパラート(ガラス板)を置く場所 |
| ステージクリップ | プレパラートを固定するクリップ |
| 粗動ねじ・微動ねじ | ピント(焦点)を合わせるための調整ねじ |
| 絞り(しぼり) | 明るさ・コントラストの調整装置 |
| 光源・鏡 | 下からプレパラートを照らす光の仕組み |
顕微鏡のしくみは、光学顕微鏡の基本として、学校でもよく出てきます。
パーツをひとつずつくわしく解説!
接眼レンズ(せつがんれんず)
目を近づけてのぞくレンズです。倍率10倍のものが多く、総合倍率=接眼レンズ×対物レンズで決まります。
10倍の接眼レンズと40倍の対物レンズなら…400倍!
あわせて読みたい:
👉 顕微鏡の倍率とは?見える大きさ・計算方法をわかりやすく
対物レンズ(たいぶつれんず)
プレパラートの上にある“メインの拡大レンズ”。
4倍、10倍、40倍などの倍率があり、レボルバーを回して切り替えます。
レボルバー
対物レンズを固定している回転部分。
「カチッ」と音がするまで回して、きちんと倍率を変えましょう。
ステージ
プレパラートを置く“観察のステージ”。
ステージクリップでしっかり固定しないと、ちょっとの振動でピントがズレてしまいます。
粗動ねじ・微動ねじ
ピントを合わせるときに使うねじです。
- 粗動ねじ:ググッと大きく動かす
- 微動ねじ:ソロ〜リと細かく動かす
「見えない!」というとき、まず見直したいのがこのねじの使い方です。
絞り(しぼり)・光源
観察する対象を明るく、くっきり見せるための調整機構です。
ガラス板の名前、ちゃんと区別できる?
顕微鏡で観察するときに使う“ガラス板”には2種類あります。
| 名前 | 説明 |
|---|---|
| スライドガラス | 標本をのせる下のガラス |
| カバーガラス | 標本の上にそっとかぶせる、うすくて小さいガラス |
「スライド=下」「カバー=上」と覚えるとバッチリ!
顕微鏡を使うときの注意点
- いきなり高倍率にしない(まずは低倍率!)
- レンズにさわらない(指紋で見えにくくなります)
- ピントが合わないときは焦らず「粗動→微動」の順で
- プレパラートはステージにしっかり固定
- 使い終わったら、乾いた布でプレパラートとレンズをやさしくふく
親子トークタイム!「この部品って、なにに見える?」
「これ、な〜んだ?」クイズで楽しく覚えよう!
- 接眼レンズ:のぞくところ…だけど「ロボットの目」っぽい!
- 対物レンズ:ズームレンズ?いや、バクテリア探知機だ!
- レボルバー:くるくる回るぞ!まるで変身スイッチ!
- ステージ:プレパラートの舞台。ミクロな世界のダンスフロア♪
- 粗動ねじ:ガガッと動く力持ちアーム
- 微動ねじ:そ〜っと動く、理科室の忍者!
「この子は何のためにいるの?」と問いかけながら使うことで、部品に“キャラクター”が生まれます。理科がグッと身近になりますよ。
まとめ:部品の名前と役割がわかれば、もう迷わない!
顕微鏡は、ひとつひとつのパーツが**“小さな世界”を見るためのチーム**として協力しています。
どの子がどんな役目をしているのかを知っておくだけで、顕微鏡の使い方もずっとスムーズになります。
あわせて読みたい:
👉 顕微鏡の使い方を順番で覚えよう|正しい手順とコツ【図付き】